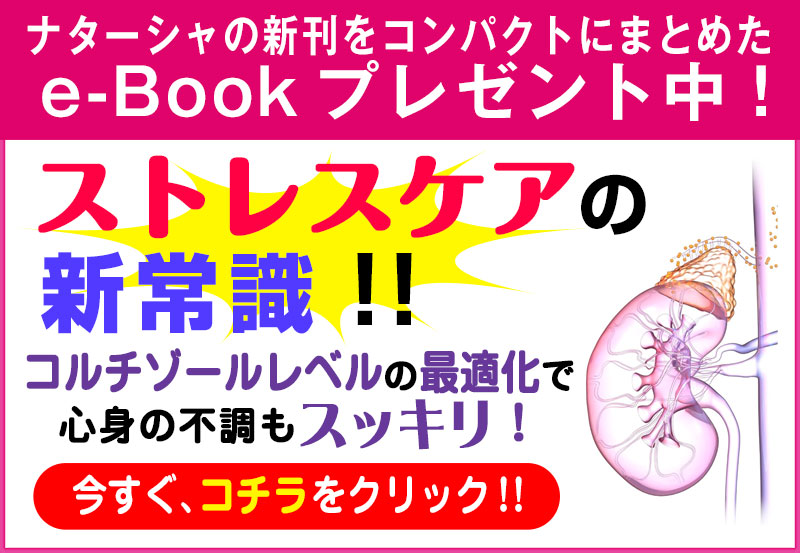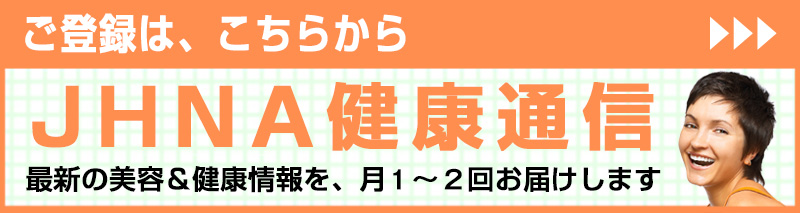JHNAストレスニュートリショニスト認定講座(全12教科)
ストレスニュートリショニストの資格取得を目指 す同講座は、ホリスティック栄養学をベースに、ストレスおよび栄養学の基礎的な知識、実践、応用までを 幅広く 、効率よく学び、すぐにセルフケアに役立てられるように カリキュラムの充実をはかっています。
<<カリキュラム>>
第1教科 ホリスティック栄養学とストレスニュートリション
認知度が高い海外とは異なり、“ホリスティック栄養学”は、日本ではまだほとんど知られていません。そこで、この教科では、ストレスニュートリション(ストレス栄養学)のベースとなるホリスティック栄養学の概念、目指すべき「健康」を明確にしていきます。ホリスティック栄養学でいうところの“オプティマルヘルス”(最上級の健康)を得るため、生化学的個体差やストレスの影響なども考慮しつつ、栄養を細胞レベルから考えていくことの重要性を学びます。
≪主な内容≫
- ホリスティック栄養学の基本概念を従来の栄養学との比較でみていく
- オプティマルヘルスを目指すために必要な栄養条件とそれを阻害する要因を考える
- 酵素に対する正しい知識を習得する
- 個体差とはどういうことなのか、一人一人個体に合わせた療法が必須であることを理解する
- 代謝プロセスにおける、酵素&補助因子の役わり&重要性を理解する
第2教科 ストレスのメカニズム/要因と反応・身体と心への影響
現代社会においてストレスは避けられません。日々発生するストレスにどのように対応していくかによって、身体も心もさまざまな影響をうけます。この教科では、ストレスとは何か、ストレッサーの特定、ストレス時に脳内および体内でどのようなことがおこり、その影響がどのように全身に波及し、さまざまな心身のトラブルにつながっていくのか、栄養とのかかわりをマスターするために必須である、ストレスの基本を学びます。
≪主な内容≫
- ストレスとは何か、どのように心身に影響をあたえ、不適切な行動や疾病などと結びつくかを知る
- ストレス反応における適応サイクル、各ステージの心身の反応、その影響などについて探る
- 脳の構造および脳を構成する各要素、さらに神経細胞の活動について理解する
- ストレスホルモン(内分泌系)&自律神経系の働きを知り、それらの影響を考える
- ストレスの“見える化”のための各種検査およびセルフチェックの活用
第3教科 ストレスに対するホリスティックアプローチ
ストレスレジリエンスを高め、ストレス反応を解消していくストレスマネージメント法はいろいろあります。この教科では、ストレッサーとの接触を最小限にとどめ、ストレスに対処(コーピング)していく方法、また、メンタルウエルネスのためのケアをホリスティックの観点から学んでいきます。
自律神経のバランスをとり戻し、コルチゾールの分泌を調整し得る各種リラクセーションテクニックの紹介と実践、栄養が果たす役わりなどもみていきます。
≪主な内容≫
- ホリスティックの観点からストレスマネージメント&コーピングを考える
- ストレスマネージメントにおける睡眠や運動の役わりを理解する
- さまざまなリラクセーションテクニックの効果と実践
- メンタルウエルネスに対するさまざまな療法
第4教科 栄養素の種類と機能
“We are what we eat and absorb”といわれるように、私たちの身体は食事からの栄養素によってつくられ、機能しています。何をどのように摂取していくかは心身の健康にはもちろん、ストレスレジリエンスのうえでも重大課題です。
この教科では、日々食事から摂取すべき必須のマクロ栄養素(タンパク質、脂質、炭水化物)およびマイクロ栄養素(ビタミン、ミネラル)それぞれについての分類、生化学的特徴など基礎的なことを学びます。各栄養素の機能、作用のメカニズム、各栄養素の不足や過剰がもたらす症状、必須脂肪酸の驚くべき価値などにも触れていきます。
≪主な内容≫
- 各栄養素の構造的な特徴、性質、機能などの確認
- マクロ栄養素の不足あるいは過剰摂取による症状
- マイクロ栄養素の生物学的利用能に影響をあたえる要因など
- 腸内細菌叢のエサとなる「プレバイオティクス」として注目される食物繊維について他
第5教科 栄養に対する影響と脳内バランス[ストレスと栄養の関係 1]
ストレスは栄養に対してさまざまな影響をおよぼし、栄養はストレス反応/耐性に多大な影響をあたえます。この教科では、ストレスの栄養に対する影響の8ポイントを確認。とくにストレス応答により亢進するグルコース合成、消費が増大し心身に多大な影響をおよぼすいくつかのビタミン&ミネラル、脳内の神経伝達物質の原料となるアミノ酸とその代謝プロセスなどについてみていきます。ストレス時の食傾向をとらえ、ストレスが心と身体にもたらす多種多様な反応と栄養との密接な関係を学びます。
≪主な内容≫
- ストレスの栄養に対する影響8つのポイントを確認する
- ストレス時のグルコース合成亢進について理解し、その影響を知る
- ストレスで消費されるビタミン&ミネラルの再確認
- 神経伝達物質の脳内での機能の理解と、栄養素との関わり
- 心のバランス=脳内バランスを整えるための栄養素、腸内環境などについて
第6教科 消化吸収と腸内環境[ストレスと栄養の関係 2]
ストレス時には多くの栄養素が必要になるにもかかわらず、消化力は低下し、また、腸内環境の悪化により必要な栄養素の確保が難しくなります。さらに、“リーキーガット(漏れやすい腸)”の発生が、身体と心の不調を誘発します。この教科では、食物や栄養素の消化/吸収と腸内環境の重要性を理解するため、消化器官と分泌腺の機能、消化酵素の働き、さらにはストレスと腸内環境、腸内微生物の影響、腸免疫、脳腸相関などについて学びます。腸内環境にまつわる各種検査もみていきます。
≪主な内容≫
- 消化と吸収のプロセス関わる消化器官、酵素の役わりと消化における重要性を理解する
- ストレスと腸内環境の関係、腸内微生物、腸内免疫、脳腸相関などについての理解を深める
- ディスバイオーシス、カンジダ菌の増殖、SIBO、リーキーガット症候群について理解する
- プレバイオティクス、プロバイオティクス、そして、ポストバイオティクスについて
第7教科 体内クレンズとデトックス[ストレスと栄養の関係 3]
ストレスは身体の解毒プロセスに影響をあたえ、さまざまな体調不良の原因となり、さらなるストレスにつながります。この教科では、デトックスの主たる器官である肝臓での「解毒」を中心に、効率的に体内の有害物質を排出するための方法、デトックスのための栄養条件の整えかたなどをみていきます。どのようなものが身体にとって有害になるのか、環境有害物質などが健康に与える影響、ストレスとの関係などとともに、特定の栄養素やハーブ類をつかってホリスィックな体内クレンズ&デトックス法を学びます。
≪主な内容≫
- デトックスとはどのようなことなのか、ストレスとの関係を探る
- 解毒のPhase1、Phase2、Phase3を理解する
- さまざまな毒物物質の特徴、それらの発生原因、接触回避方法などを考える
- 身体がもつ自然の解毒&浄化システムをサポートする食品や栄養素の確認
- デトックス力をサポートするための方法とその実践。ファスティング、キレーションについて。
第8教科 活性酸素対策 悪玉酸素の陰謀[ストレスと栄養の関係 4]
ストレスは、とびきり強力な活性酸素の発生を誘発します。このとき体内に抗酸化物質(栄養素)が不足していたら、身体は有害な酸素の害をうけ、心身共に破たんへの道をすすむことになります。この教科では、活性酸素/フリーラジカルの正体を暴きながら、心身へのダメージがどのようなものなのか、身体を守る抗酸化メカニズムなどをみていきます。抗酸化栄養素とそれらの働き、さらにはフィトケミカルなどの知識を深め、効果的な酸化ストレスの対応法などを学びます。
≪主な内容≫
- 活性酸素の正体を知り、どのようなトラブルをひきおこすのかを確認
- 抗酸化ネットワークの生理機能/抗酸化物質とフリーラジカルの攻防戦をみる
- 抗酸化栄養素とフィトケミカルを理解する
- 酸化ストレスを防ぎ、身体を守るために効果的な活性酸素対策を考える
第9教科 ストレスに打ち勝つ食事の原則1
ここからは、これまで学んできたストレス、そして栄養の知識を実際の生活にどのように活かしていけばいいのか、実践編にはいっていきます。
ストレスレジリエン&スストレス反応からの回復には健康的な食生活は必須です。この教科では、ストレスに強い心身づくりのための基本である、「食事の原則6つのポイント」のうち、4つのポイントについて確認します。極力排除すべき食品や飲み物、食生活において血糖値の安定を意識することの重要性、賢い油脂のとりかた、主食・副食の賢い選び方や食べ方などを学びます。
≪主な内容≫
- 特定の食品&飲み物がどのようにストレスの悪化を招き、身体にダメージをあたえるかを知る
- 好ましい三大栄養素の選択と、その選択をいかに日々の食生活に活かすかを考える
- 健康維持または向上のために必要な各栄養素の摂取量やバランスについて考える
- 糖質制限食についての理解を深める
第10教科 ストレスに打ち勝つ食事の原則2
この教科では、「食事の原則6つのポイント」の残りの2つのポイントをみていきます。マクロ栄養素の配分を考えた食事を準備するのは大切ですが、口にする食事から最大のメリットを得るためには、食材選びから、貯蔵法、調理法や食べ方まで考えていく必要があります。全体食を選択とることの意味、食べ方の工夫、見直すべき食習慣などとともに、マクロビオティックをはじめ、さまざまな食事法の特徴、実践のメリット&デメリットを学んでいきます。
≪主な内容≫
- SN栄養学でWholeWholeFoodFoodがなぜ推奨されるのか、加工食品、農産/畜産物の実態を知る
- 栄養素を最大に活かすための食物の選択、保存法、調理法、食べ合わせなどをマスターする
- 変えるべき食習慣改善のためのヒントをつかむ
- 各種食事法(ベジタリアン、マクロビオティック他)の特徴&問題点などを把握する
第11教科 サプリメントの選択と利用法
ストレス時には普段以上に多くの栄養素が消費されていくため、通常の食事だけでは必要な栄養素の確保が難しくなります。この教科では、まず、サプリメントの基本をおさえたうえで、ストレスレジリンスの向上のためや、ストレス反応によるダメージを最小限に抑えるためのサプリメントの選択と摂取法、さらに、ストレス反応が強くでているときのメディシーナルハーブ、アミノ酸系サプリメントなどについて学びます。
≪主な内容≫
- サプリメントの原材料、添加物、製造法、購入時のチェックポイントなどの確認
- サプリメントの基本的な摂取法や注意点などのおさらい
- ベースとなる必須栄養素のサプリ、スポットサプリなどの役わりの把握
- コルチゾールの上昇を招く、ストレス時にNGの成分とサプリを知る
- アダプトゲン、抗ストレスサプリ、リラックス&鎮静サプリなどの選択と摂取のしかた
第12教科 ストレス関連症状別栄養療法 アドバイスの実践
慢性ストレスは、あらゆる身体&心のトラブルにつながります。食生活の改善およびストレスコーピングが大切ですが、すでに身体になんらかのトラブルが発生している場合には、具体的なプロトコルが必要になります。この教科では、ストレスによって発生しやすいいくつかの身体のトラブルに対する栄養療法の実際をみていきます。
≪主な内容≫
- ストレスによる摂食障害(拒食症/過食症)、ダイエットなどについて理解する
- 遅延型食物アレルギーと食物不耐性の違いを知り、それぞれの対応を考える
- 腸壁/腸粘膜の修復について考える
- 「ダイジェスティブ・ヘルス」のための食べ物、ハーブ、ライフスタイル、サプリメント戦略のまとめ
- ストレス関連のトラブルとして多い、カンジダ症/イースト感染、消化不良/胸やけ、消化不良症候
群、過敏性腸症候群(IBS)、疲労症候群などの栄養療法を確認